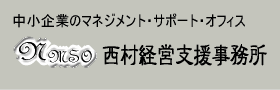 |
||
|
|
||
| 1.病院経営を取り巻く環境 2.医療の質とは 3.医療の質マネジメントシステムの種類 |
| 4.質のマネジメントの8原則 5.マネジメントシステム構築のポイント 6.医療の質の向上策 |
| 7.システム構築に要する期間 目次へもどる (注)印刷する場合は用紙の向きを横に設定してください。 |
|
|
| マネジメントシステム構築のポイント | |||
| |
|||
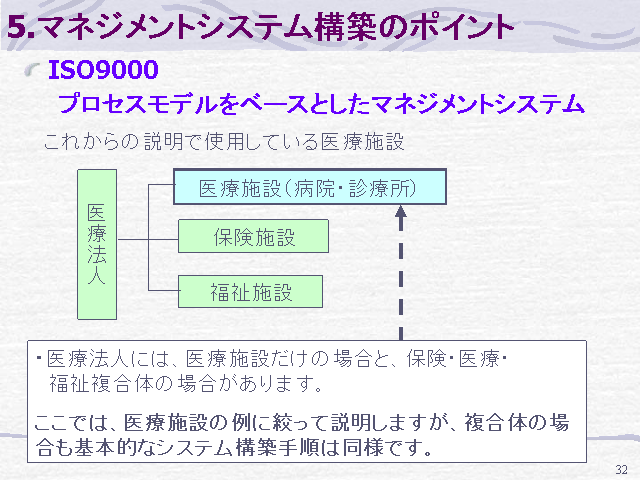 |
?
この章では、ISO9000をモデルにして、マネジメントシステム構築のポイントを説明します。 医療法人に医療施設、保健施設、福祉施設が含まれているケースがあると思いますが、ここでは医療施設の例に絞って説明します。 しかし、基本的なシステム構築手順はどの場合も同じです。 |
||
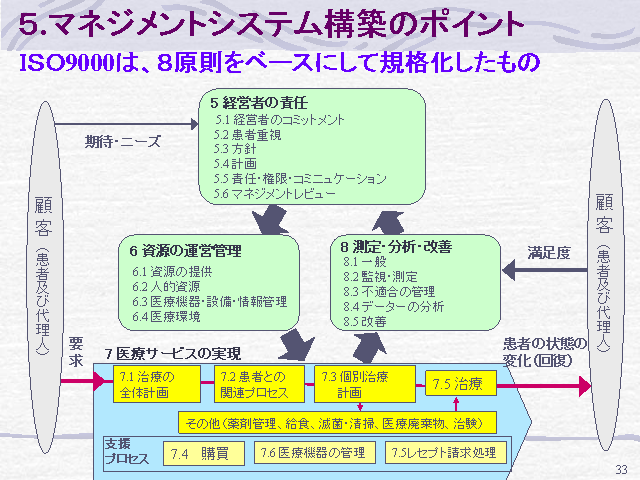 |
これは、ISO9000のプロセスモデルです。 経営という観点から見た場合、Plan−Do−Check−Actonの流れは「経営者の責任(役割)」「資源の運用管理」「医療サービスの実現」「測定・分析・改善」というプロセスに分けられます。 ISO9000規格は、このプロセスごとに要求事項(何をしなけらばならないか)を定めています。 このプロセスごとに、システム構築のポイントを説明していきます。 |
||
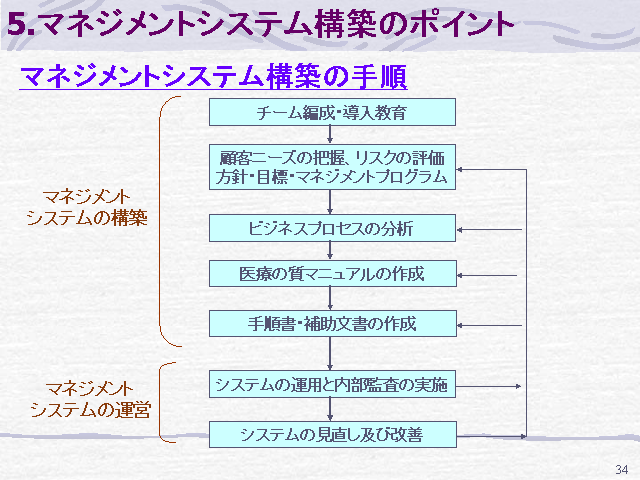 |
システム構築の流れを説明します。 最初にチーム編成と導入教育を行います。 次に顧客(患者・家族)のニーズや経営環境を調査し、方針と活動目標を定めます。 活動目標というのは、改善を目指したものですが、一方、方針を達成するために標準化し維持していくものをあります。 標準化は、ビジネスプロセスを特定して、重要なプロセス単位に行います。 標準化の過程は、仕事の運用の考え方を書いた「医療の質マニュアル」と、そのマニュアルに従って作成する個々の業務手順類、の2段階があります。 標準化ができると、関係職員に教育し運用してみます。 内部監査を行って、構築したシステムが有効に機能するかを確認します。 その後、患者満足度や内部監査・改善の達成度などをまとめ分析して、マネジメントシステムそのものが目的に合っているかを確認します。 合っていなければ、方針やしくみの修正が必要になります。 |
||
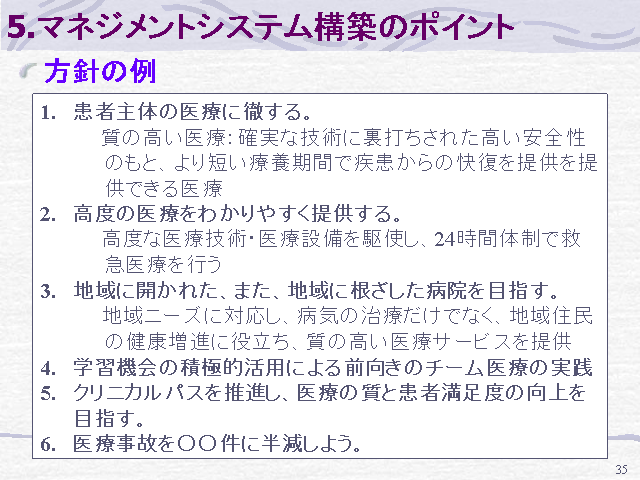 |
これは、品質方針の一例です。 病院機能評価の場合は、基本方針と呼んでいます。 |
||
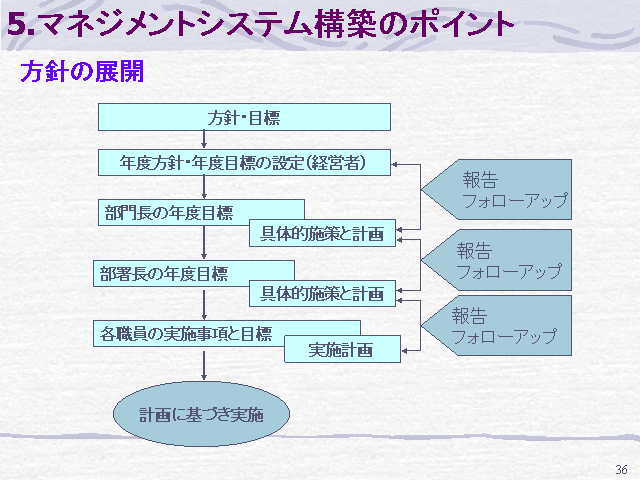 |
基本方針(あるいは品質方針)というのは、3年程度の先を見越した中期的なものです。 この方針に対して、年度ごとの方針と目標を定めます。 年度目標は、部署ごとに具体的な施策まで展開します。 活動の経過及び結果は、適宜、上司あるいは委員会に報告し問題があれば修正措置をとります。 |
||
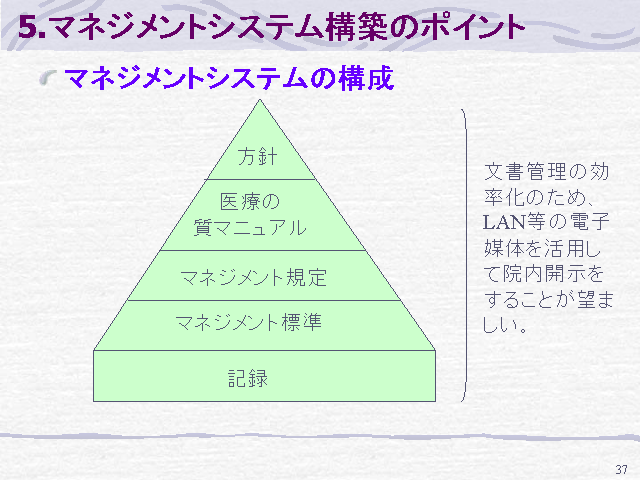 |
どの病院においてもマネジメントシステムは既に存在しています。 マネジメントシステムを継続的に改善していくためには、一度、目に見える形にする必要があります。 このことを、マネジメントシステムの文書化といいます。 マネジメントシステム文書の構成は ・方針 ・方針に基づいて、医療業務の運用の考え方を書いた「医療の質マニュアル」 ・主要プロセスごとに誰が、何をするかを定めた規定 ・特定の業務について、どのように行うかを定めた標準 ・活動結果の記録 で構成されたいます。 文書は、常に正しい状態に維持しておく必要があります。 文書管理を効率的に行うにはLANなどの電子媒体を活用することをお勧めします。 |
||
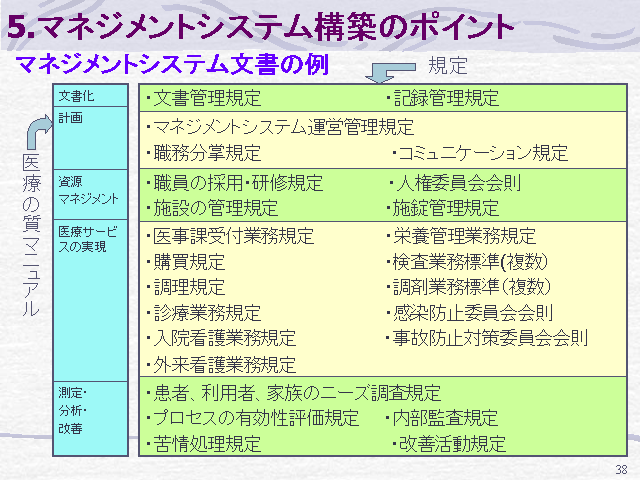 |
これは、マネジメントシステムの文書化の例です。 左の空色の部分が「医療の質マニュアル」の章構成で、右側にマニュアルの章に対応した規定の種類が書かれています。 |
||
 |
それでは、次にマネジメントのプロセス単位にポイントを説明します。 先ず、経営者の責任(役割)というプロセスには、顧客重視という条項があります。 顧客重視とは、 医療を受ける者の要求事項を知ること、そして知る権利の尊重と情報の提供ということがあります。 その例としては ・診断及び治療に関わる情報の提供 ・レセプトの開示 ・診療録の開示 ・患者の相談窓口の設置 ・方針、指針などの公開 と行ったしくみの整備があげられます。 |
||
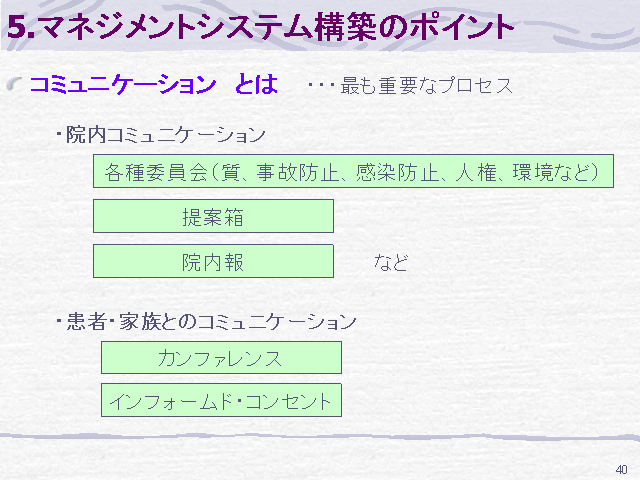 |
コミュニケーションには、院内コミュニケーション、患者・家族とのコミュニケーションの両方があります。 院内コミュニケーションでは、どの委員会で何を話し合うか、その役割・責任を明確にして運営していくしくみが必要です。 また、職員の意見をマネジメントに反映させるために提案箱、院内報なども有効です。 患者・家族とのコミュニケーションとしては カンファレンス インフォームド・コンセント などのプロセスを定める必要があります。 |
||
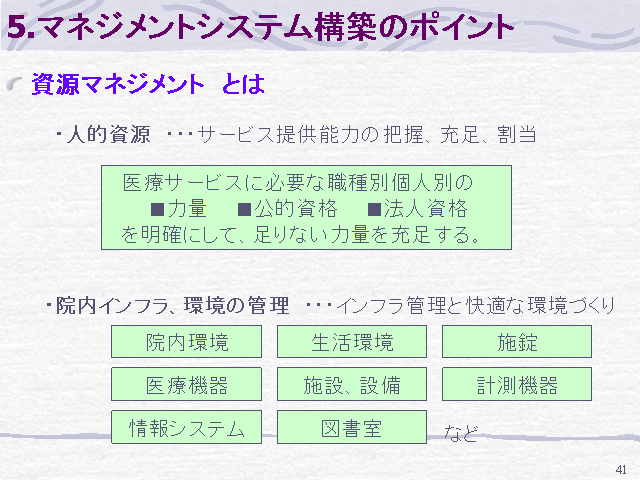 |
資源マネジメントのプロセスでは、人的資源の管理と院内インフラ・環境の管理があります。 人的資源の管理とは 業務上必要な知識・技量を明確にしてスキルを向上していくための体系的な教育・訓練プログラムを作ることです。 院内インフラ、院内環境の管理 ISO9001では、病院側の責任において、必要な設備・医療機器・医療環境・生活環境を特定し、維持管理していくことです。 しかし、病院機能評価では、これらについての細かい基準が設けられています。 ですから、ISO9000では不適合とはならなくても、病院機能評価では不合格ということもあり得ます。 |
||
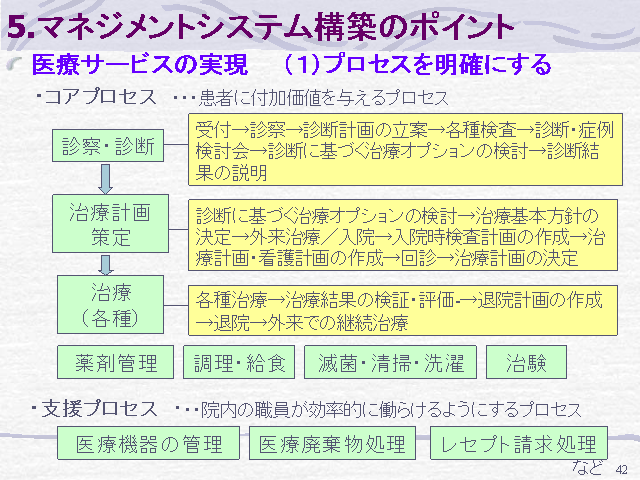 |
医療サービスの実現のプロセスですが、このプロセスを構築するには (1)必要なプロセスを明確にする (2)特定したプロセスごとに、よい手順を定める。 (3)特定したプロセスの監視・測定項目を定める。 という順序で行います。 必要なプロセスの特定 右は、プロセスの特定の例ですが、コアプロセスー患者に付加価値を与えるプロセスーとしては ・診察、診断 ・治療計画策定 ・各種治療 ・薬剤管理 ・調理、給食 などがあげられます。 支援プロセスー院内の職員が効率的に働けるプロセスーとしては ・医療機器の管理 ・医療廃棄物処理 ・レセプト請求処理 などがあげられます。 |
||
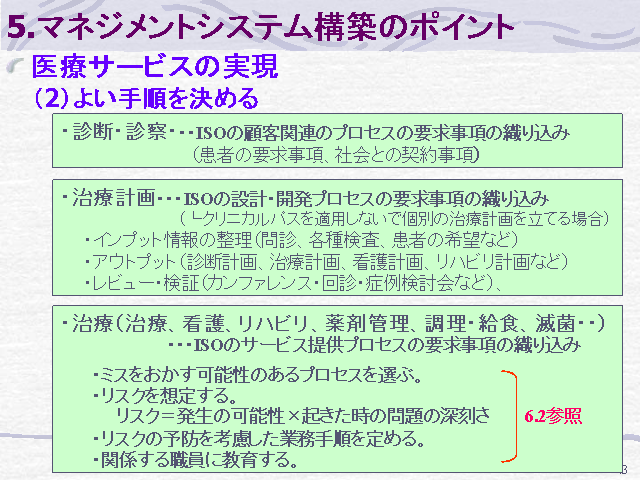 |
(2)これらの特定したプロセスに対して、よい手順を定めます。 診察・診断のプロセスでは、ISO9001 7.2項 顧客関連のプロセスの要求事項を織り込んでいきます。 治療計画のプロセスには、クリニカルパスを使用する場合と、患者個別の治療計画を立てる場合があります。 患者個別の治療計画を立てる場合は、ISO9001 7.3 設計・開発の要求事項を織り込んでいきます。 治療のプロセスでは、医療過誤を予防する適切な業務手順を定めます。 ここのところのやり方については、後程のスライド 6.2項 で詳しく説明します。 |
||
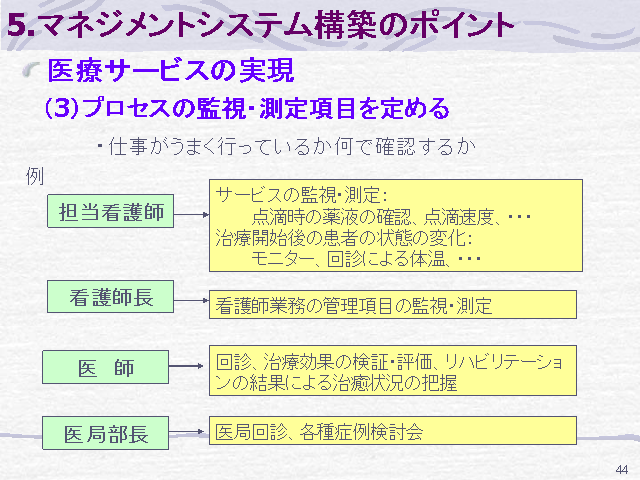 |
(3)プロセスの監視・測定項目を定める。 各職位ごとに、仕事がうまく行っているかどうか、何で確認するかを定めます。 この中で、数値データとして出てくるものが測定で、その他のものが監視と解釈してください 。 例えば、 担当看護師さんは、点滴時の薬液の確認、点滴速度・・・ 看護師長は看護師業務の管理、看護主任の巡回・・・ といったことです。 |
||
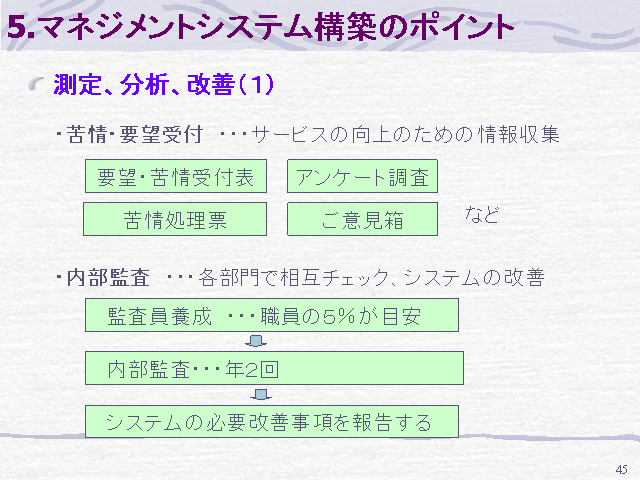 |
測定・分析・改善のプロセスは、マネジメントシステムがうまくいっているか確認し分析するプロセスです。 患者満足や苦情、内部監査、目標の達成状況、医療過誤などの不適合の発生状況のデータを収集し分析します。 苦情・要望受付 アンケート調査やご意見箱などにより患者・ご家族の意見や苦情を収集します。 内部監査 業務が適切に効率的に行われているかどうか、診療科同士、職種間同士で相互監査を行います。 回数は年2回程度、結果を被監査部門と経営者に報告します。 |
||
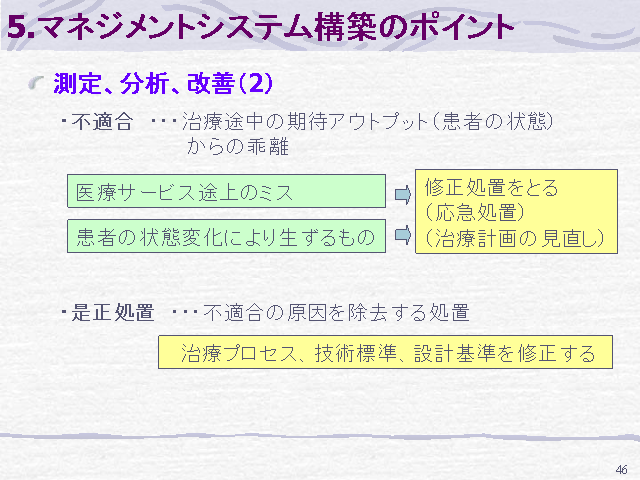 |
不適合 不適合とは聞きなれない言葉かもしれません。 不適合とは、要求事項を満たしたいないことです。 医療サービスの場合は、治療途中の期待アウトプットが時間経過とともに期待から外れて行くことです。 これには医療サービスのミスの場合と患者の状態変化により生ずる場合があります。 いずれの場合も、応急処置をとり、結果を記録しておくことが必要です。 是正処置 是正処置とは、不適合の原因を分析して、次の治療プロセス、標準に織り込んでいくことです。 |
||
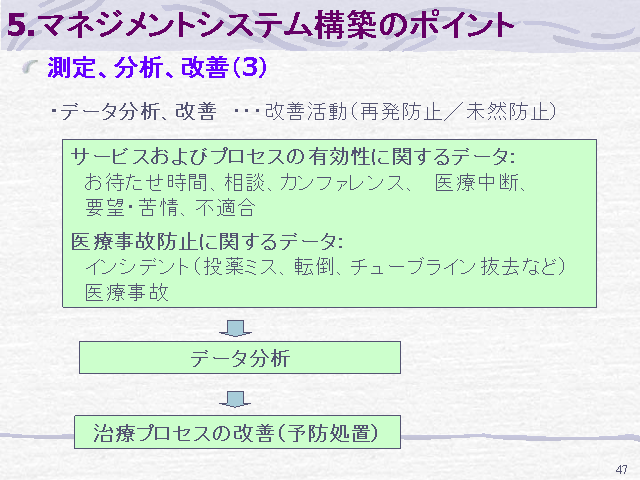 |
データ分析・改善 不適合やサービスプロセスの目標からの外れ、アクシデント、インシデントなどのデータを収集・分析し治療プロセスに織り込んでいきます。 ISO9000では、このことを予防処置といっています。・ |
||
|
|
|||
| BACK ← →NEXT | |||
| コンピテンシーマネジメント ⇒ 福祉・介護の人材育成の進め方 | |||