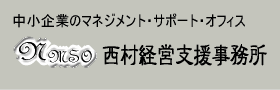 |
||
|
|
||
| 1.病院経営を取り巻く環境 2.医療の質とは 3.医療の質マネジメントシステムの種類 |
| 4.質のマネジメントの8原則 5.マネジメントシステム構築のポイント 6.医療の質の向上策 |
| 7.システム構築に要する期間 目次へもどる (注)印刷する場合は用紙の向きを横に設定してください。 |
|
|
| 質のマネジメントの8原則 | |||
| |
|||
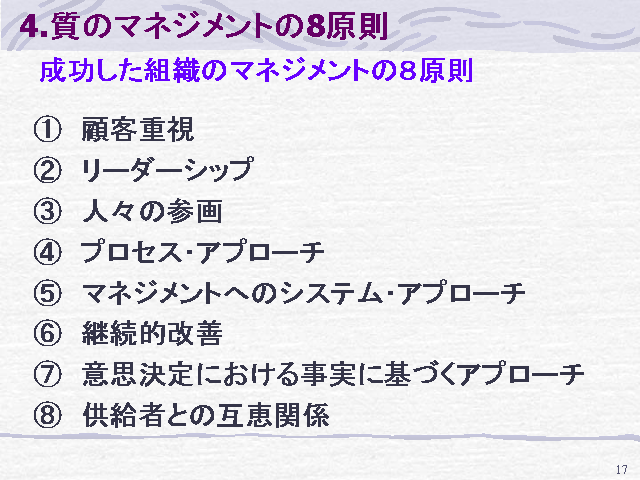 |
?
質のマネジメントの8原則 マネジメントシステムには考え方のベースとなっている原則があります。 ISO9000規格制定委員会(TC176)は、世界の中で経営が効果的に行われている会社について共通的な原則を調査しました。その原則が「品質マネジメントの8つの原則」としてISO9000及び9004に紹介されています。
ISO9000シリーズ規格は、この規格を適用する組織が、8つの原則を適用し、良い組織となっていくことを目指しています。
ですから、この原則をよく理解することがISO9000シリーズに沿ったマネジメントシステムを構築する近道となります。
次に、この原則を医療に適用した場合を想定して、順番に説明していきます。 ?
|
||
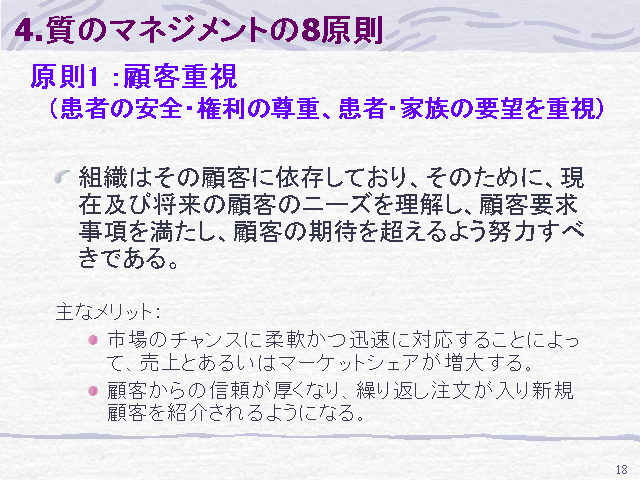 |
原則 1 顧客重視 医療では、患者の安全・権利の尊重、患者・家族の要望の重視 という意味です。 組織はその顧客に依存しており、そのために、現在及び将来の顧客のニーズを理解し、顧客要求事項を満たし、顧客の期待を超えるよう努力すべきである。
その結果として、
・売上とあるいは市場シェアが増大する。
・リピート客や新規患者を紹介されるようになる。
といっています。
ここで、注意すべきことは
・患者・家族のニーズを理解すること
・患者の要求事項を満たし、更に期待を超えるよう努力することです。
。
|
||
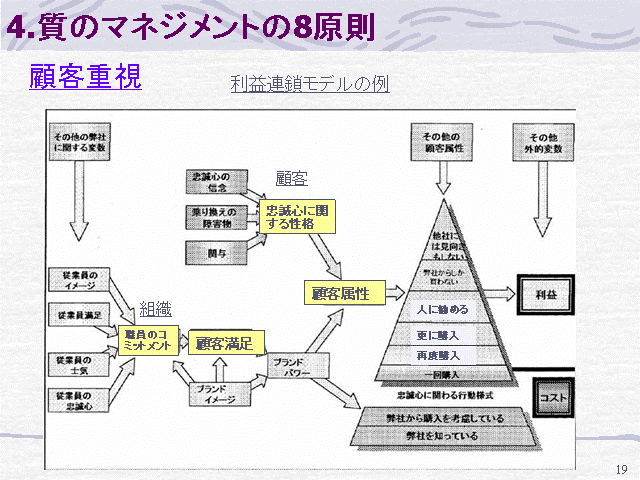 |
この図は、民間企業における顧客重視と利益額の連鎖の図です。 この図の顧客というところを、患者と置き換えてください。 病院においても同じことが言えると思います。 |
||
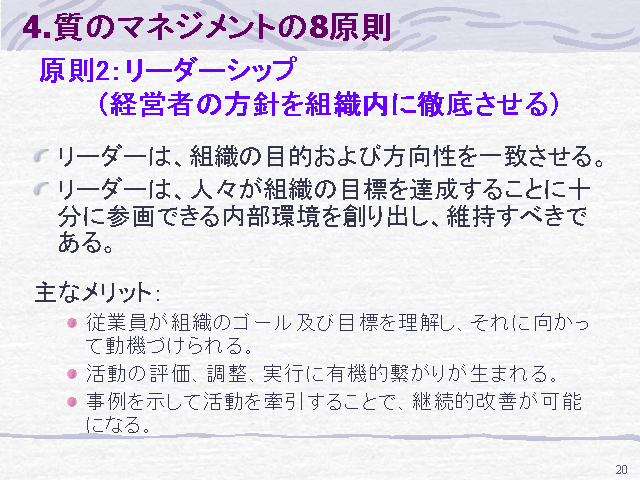 |
原則 2 リーダーシップ ここでいうリーダーとは、病院のトップのことを指しています。
リーダーは、組織の目的および方向性を一致させる。
リーダーは、人々が組織の目標を達成することに十分に参画できる内部環境を創り出し、維持すべきである。
その結果として、職員の間に共通の目標が生まれ、働き甲斐の向上と情報の共有化が進み、継続的な改善が進むようになるといっています。
最近の例では、日産自動車のゴーン社長がとられた行動・ケースが、ここで言っているリーダーシップの良い例です。
|
||
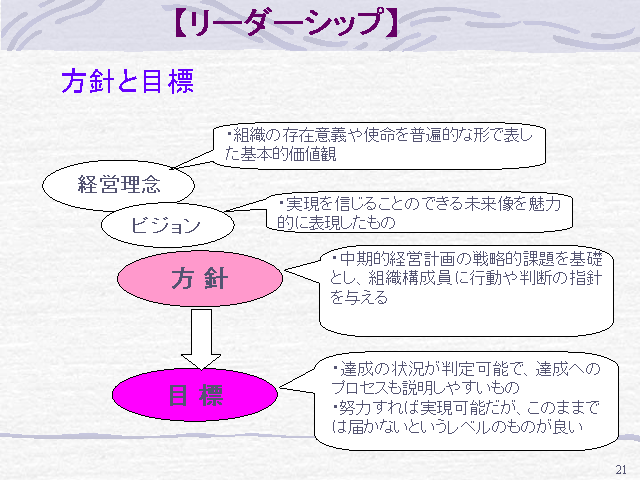 |
組織の目的は、経営理念やビジョンによって表現されます。
この目的を達成するための戦略が方針です。 方針は、3〜5年位を見越して建てられます。
方針を達成するためのそれぞれの方策が目標で、目標には誰が、いつまでに、何を達成するかは測定可能な指標で示される必要があります。
また、目標を達成するための手段は、アクションプランまたはマネジメントプログラムと呼ばれ、部門目標から個人の自主的な目標まで展開されることが望ましい姿です。
リーダーシップとは、目的・方針を明確にし、方針・目的に従って各個人が自主的に目標を定めて活動できる環境を整えるということでもあります。
|
||
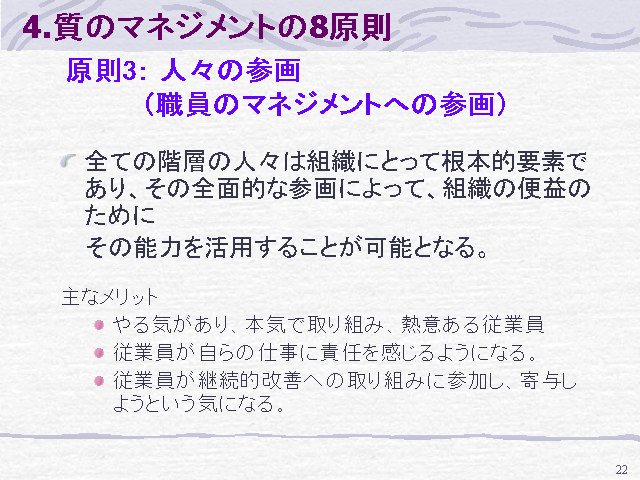 |
原則 3 職員のマネジメントへの参画 全ての階層の人々は組織にとって根本的要素であり、その全面的な参画によって、組織の便益のために その能力を活用することが可能となる。 その結果として
やる気があり、熱意ある職員が生まれ継続的改善が進むといっています。
職員の全面的な参画を得るには、次の3つの観点から施策を考えていく必要があります。 (1)組織の価値観に基づき、職員が自主的に行動できる環境を作る、最適配置、情報の共有化、各自が定めた目標に対して実績を評価し役割を認める、など組織全体の能力を高めること
(2)業務に必要な能力を明らかにし、職員に能力開発の機会を積極的に提供すること
(3)職員の組織に対する満足・不満足、意見、要望などを把握し問題点や制約条件を改善する。 また安全管理や福利厚生などへの支援も必要になってきます。
|
||
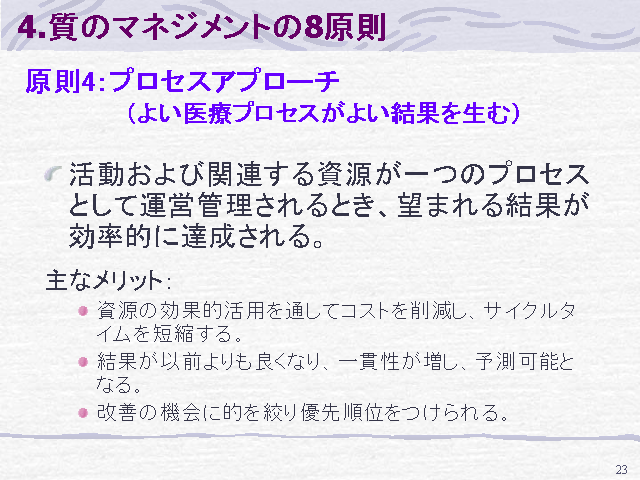 |
原則 4 プロセスアプローチ プロセスは、目的を持った活動の集まりです。 活動および関連する資源が一つのプロセスとして運営管理されるとき、望まれる結果が効率的に達成される。
その結果として、
資源の効果的活用を通してコストを削減し、効率が向上され、業務の管理・改善がやりやすくなるといっています。
プロセスとは、工程ともいわれ製造業では、馴染みのある言葉ですが、医療では馴染みがないかもしれません。 「よいプロセスがよい結果を生む」ということが考え方の基本です。 |
||
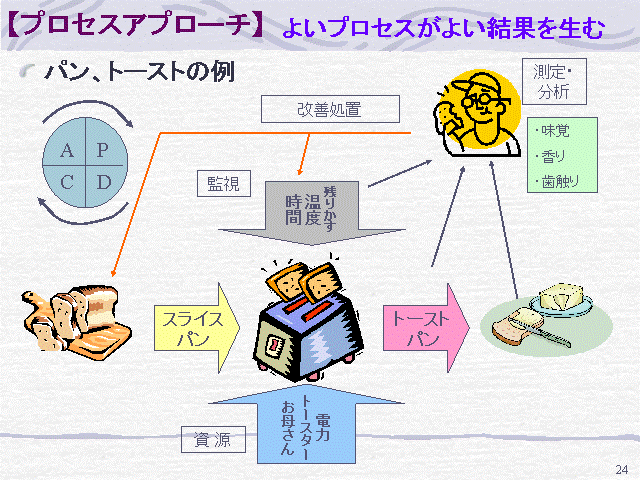 |
プロセスは、インプットをアウトプットに変換し、その過程で付加価値を与える活動です。 ここで皆さんが、朝、会社に出勤する前にパン食を取るとときのことを考えて見てください。
インプットはスライスパンで、アウトプットは焼きあがったトーストパンです。 スライスパンをトーストパンに変える過程がトーストプロセスということになり、資源はトースター・電力・パンを焼いてくれるお母さん、管理項目は温度・時間です。
おいしいトーストパンを焼くには、スライスパンの選択、温度、時間を設定し焼いて見ます。 最初に焼いたパンの味・香り・焼き具合を確認します。 その結果、問題があれば原因を推定し、例えば温度や時間を変えて見ます。
この過程を繰り返していくうちにおいしいトーストパンが焼けるプロセスが明確になってきます。
これが、プロセスの標準化ということです。
医療においても、同じことで「正しいプロセスを明確にする」ということが医療過誤の防止に役立ちます。
|
||
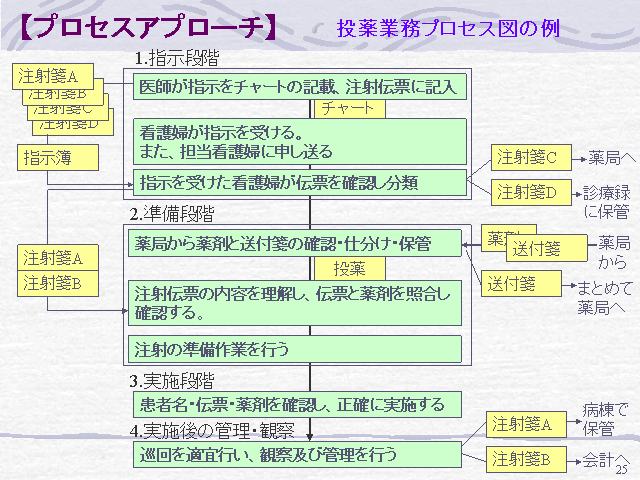 |
これは、投薬業務プロセスの標準化の例です。 このように、正しいプロセスを定めて、守り、また改善して行くことが大切です。 |
||
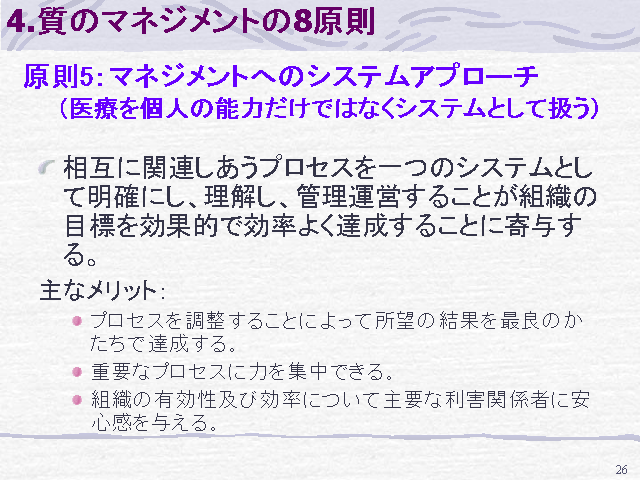 |
原則 5 システムアプローチ 相互に関連しあうプロセスを一つのシステムとして明確にし、理解し、管理運営することが組織の目標を効果的で効率よく達成することに寄与します。
その結果として
所望の結果を最良のかたちで達成でき、また重要なプロセスに力を集中できる
といっています。
医療においては、特に、医師個人の能力で治療を行うのではなく、システムとして治療していくしくみが大切ということでしょう。 |
||
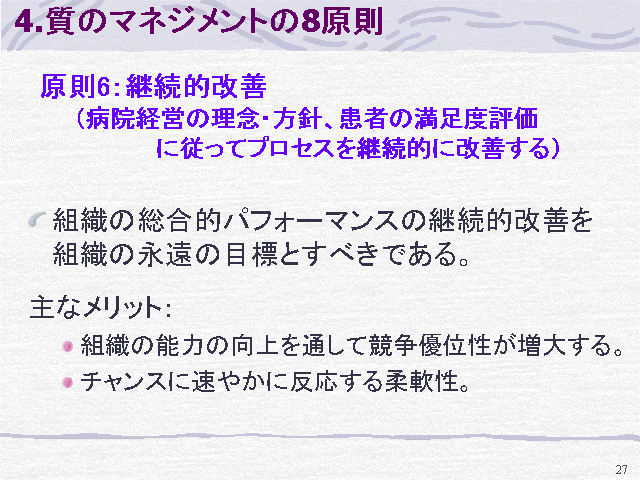 |
原則 6 継続的改善 組織の総合的パフォーマンスの継続的改善を組織の永遠の目標とすべきである。
その結果として
組織の能力の向上を通して競争優位性が増大する。
チャンスに速やかに反応する柔軟性が培われる。
といっています。
総合的パフォーマンスとは、組織によって違ってきますが、病院においては例えば 患者満足度、リピート率、患者さまご意見箱に寄せられた苦情件数などの指標で測定することができます。
|
||
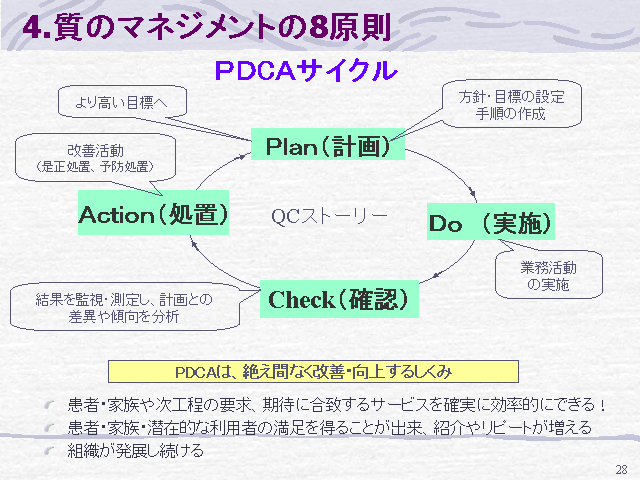 |
継続的改善とは、総合パフォーマンス指標の向上を目指して、Plan、Do、Check、Actionのサイクルを繰り返しまわしていくことです。
そのためには
・ISO9000は継続的改善のしくみですので、ISO9000を良く理解し、規格の主旨に
従って組織を運営すること。
・組織のパフォーマンス指標とゴールを明確にすること。
・職員に改善手法・ツールに関する訓練を提供すること。
・達成された改善についてはこれを認め、労をねぎらうこと。
といった施策が必要です。
|
||
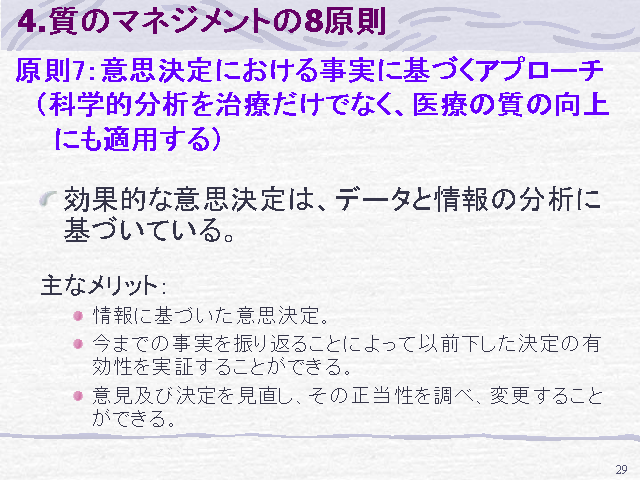 |
原則 7 事実に基づくアプローチ 効果的な意思決定は、データと情報の分析に基づいている。
その結果
情報に基づいた正しい意思決定ができるようになるといっています。
病院では、医療機器を用いて科学的なデータにもとづいた治療が行われています。
ここでは、このような科学的なデータによる管理を経営にも使うことを勧めています。 |
||
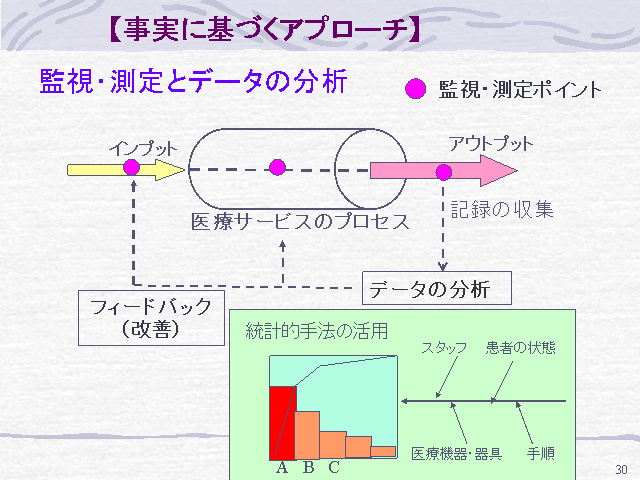 |
例えば、医療のプロセスで医療過誤が発生した場合、統計的手法を活用して、その原因を分析し再発防止を図るといったことを指しています。 |
||
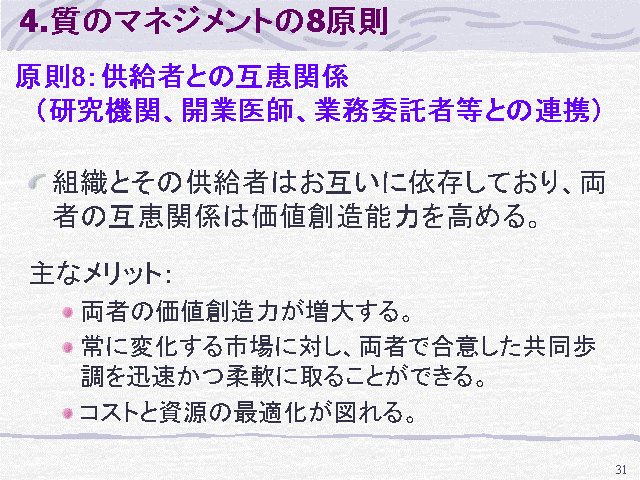 |
原則 8 パートナーとの連携 ここでいう供給者とは、パートナーという意味合いを含んでいます。
組織とそのパートナーはお互いに依存しており、両者の互恵関係は価値創造能力を高める。
その結果として
両者の価値創造力が増大し、チャンスに柔軟に対応でき、コストと資源の
最適化が図れる。
といっています。
研究機関、開業医師、委託業者と、お互いの専門知識と資源を活用する形での長期・短期のバランスの取れた関係を築くことが重要です。 |
||
|
|
|||
| BACK ← →NEXT | |||
| コンピテンシーマネジメント ⇒ 福祉・介護の人材育成の進め方 | |||